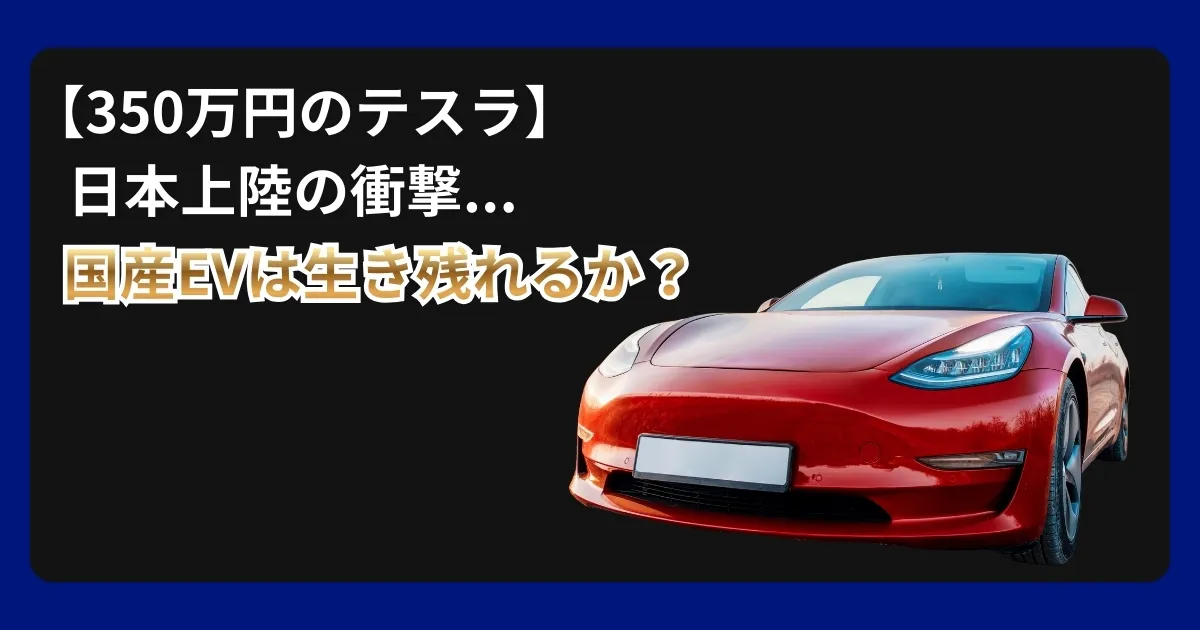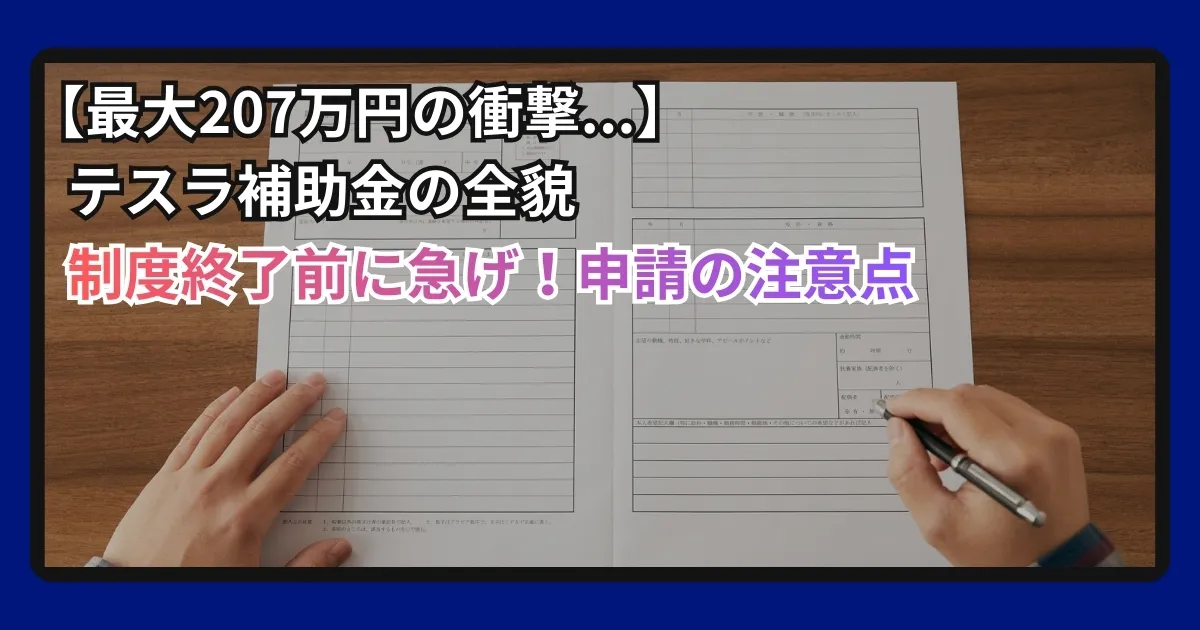どうなる?日本のクルマの未来。高市新総裁の政策から読み解く「確定事項」と「今後の予測」

日本の新しいリーダーに、高市早苗氏が就任しました(※本記事は2025年10月の総裁就任を前提とした分析です)。
新政権の船出に、日本中が固唾をのんで見守っています。
中でも、私たちの生活と経済の心臓部である自動車業界は、これからどこへ向かうのでしょうか。
EV(電気自動車)へのシフト、ガソリン価格の動向、そして世界と戦う日本のモノづくりの競争力は。
高市新総裁の誕生は、これまでの路線を加速させるのか、あるいは新たな方向性を示すのか。
その答えを読み解く鍵は、すでに動いている「確定事項」と、これから起こりうる「今後の予測」を冷静に切り分けることにあります。
本記事では、まず政府としてすでに進んでいる自動車関連の政策を整理し、その上で高市氏の過去の発言や政治信条から、未来に起こりうる4つのシナリオを詳しく分析していきます。
まずは「確定路線」から。すでに動き出しているクルマの政策

新しいリーダーが誕生したからといって、すべてが明日から変わるわけではありません。
特に、国の根幹をなす産業政策は、巨大な船のようにゆっくりと、しかし確実に動き続けています。
高市氏がこれまで深く関わってきたものも含め、「継続されることが確実」と見られている政策から見ていきます。
◆日本の技術を守る「経済安全保障」の強化
「経済安全保障」——ここ数年、頻繁に耳にするようになったこの言葉は、高市氏の政治家としてのキャリアを語る上で欠かせないキーワードであり、自動車業界の未来を占う上で最も重要な確定路線でもあります。
現代のクルマが「走る半導体」とまで言われるように、その頭脳を司る半導体や、EVの心臓部であるバッテリーの安定確保は、国家の生命線と言えます。
特定の国に供給を依存するリスクは、コロナ禍や国際情勢の緊迫化で、広く認識されるようになりました。
高市氏が経済安全保障担当大臣として成立を主導した「経済安全保障推進法」に基づき、政府はすでに具体的な手を打っています。
- 半導体: 台湾の世界的企業TSMCの熊本工場誘致や、次世代半導体の国産化を目指す新会社「Rapidus(ラピダス)」への巨額の補助金は、日本の半導体産業の再興に向けた国家プロジェクトです。
- バッテリー: EVの普及に不可欠なバッテリーについても、国内での生産拠点強化や、原料となるリチウムなどの重要鉱物を安定的に確保するための国家的な取り組みが進んでいます。
これらの動きは、高市氏個人の新方針というより、政府全体の継続的な方針です。
高市新政権では、この流れが減速することは考えにくく、むしろ「日本のモノづくりと技術を守る」という強い意志のもと、さらに加速していくことが確実視されます。
◆EVや安全運転サポート車を買うときの「補助金」
クリーンエネルギーへの転換を促すため、EVやPHEV(プラグインハイブリッド車)への手厚い購入補助金制度が現在も運用されています。
同時に、高齢ドライバーによる事故防止などを目的として、衝突被害軽減ブレーキなどを備えた「安全運転サポート車(サポカー)」の購入を支援する制度も存在します。
これらの購入補助金は、現在も経済産業省や国土交通省によって実施されている継続的な施策であり、新政権下でも短期的になくなることは考えにくい状況です。
「環境性能や安全性能の高いクルマを普及させる」という大きな流れは維持されると見るのが妥当です。
ここまでは、現政権下ですでに進行している政策、いわば「確定路線」です。
しかし、多くの人が関心を寄せるのは「これからどう変わるのか」という点でしょう。
新しいリーダーの個性や哲学は、未来の政策にどう反映されるのでしょうか。
高市氏の過去の発言や政治信条から、専門家たちが注目する「4つのシナリオ」を検証します。
高市カラーで変わるかもしれない「4つのシナリオ」
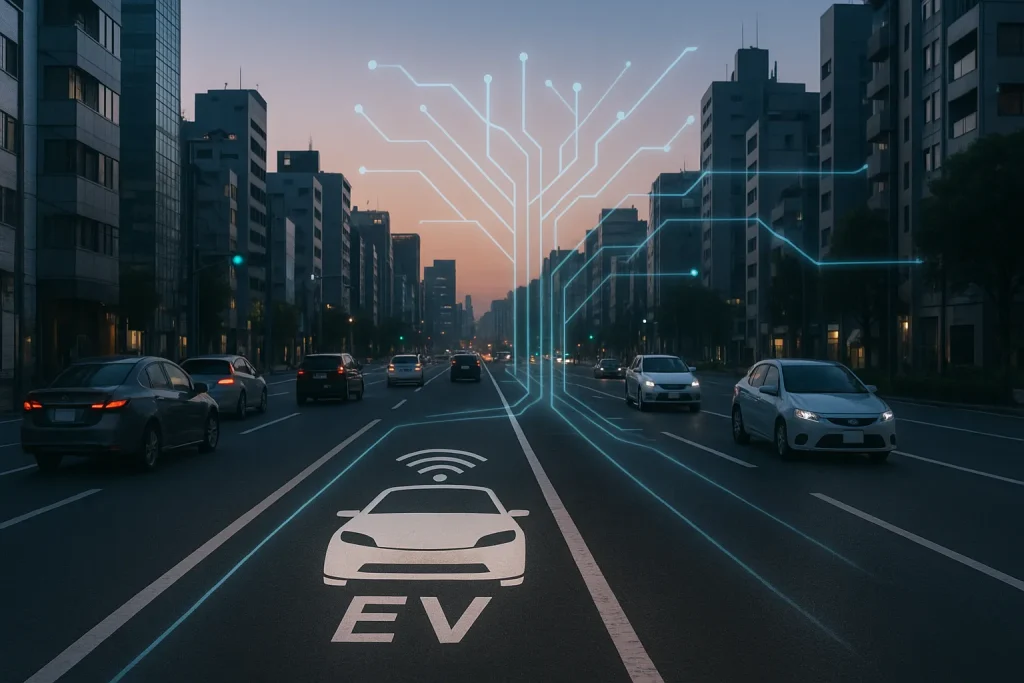
これまでは、政権が代わっても継続されるであろう政策の土台部分を見てきました。
しかし、新総裁の就任で最も注目されるのは、どのような「高市カラー」が打ち出されていくのかという点です。
高市氏のこれまでの発言や、その政治信条を基に、今後の自動車業界に影響を与えうる4つのシナリオを、ここから具体的に検証していきます。
これらはあくまで現時点での予測ですが、未来を展望する上で重要な論点となります。
◆シナリオ①:「脱・特定国依存」はさらに加速する?
先ほど触れた「経済安全保障」は継続路線ですが、ここに高市カラーが加わることで、そのアクセルがさらに強く踏み込まれるかもしれません。
特に、EVバッテリーの原料となるレアメタルなどは、その多くを特定の国(主に中国が念頭に置かれている)からの輸入に頼っているのが現状です。
もし、その国との関係が不安定になれば、日本の自動車生産は大きな打撃を受けかねません。
そのため、経済産業省はすでにオーストラリアなど他の国との連携を強める動きを見せています。
高市新政権では、この「脱・特定国依存」の流れが、より明確な国家戦略として加速していく可能性があります。
自動車メーカーにとっては、時間を要する課題ではありますが、より安全で安定した部品調達ルートを確保できる、長期的なメリットに繋がるものと考えられます。
◆シナリオ②:ついに発動?待望の「ガソリン減税」
日々の生活でクルマを使う人にとって、最も身近な問題がガソリン価格です。
高市氏は以前から、この負担を軽くするための選択肢として「トリガー条項」の凍結解除に言及してきました。
これは、ガソリン価格が一定の基準を超えて高騰した場合、自動的にガソリン税の一部(1リットルあたり25.1円)が引き下げられる仕組みです。
東日本大震災の復興財源を確保するために、現在は「凍結」されています。
高市氏は、この凍結を解除することに前向きな発言をしていますが、注意点もあります。
まず、これは総裁就任後の正式な方針としてまだ発表されたわけではないこと。
そして、仮に減税が実現しても、元の原油価格が上がってしまえば、その効果は相殺されてしまうことです。
とはいえ、家計負担の軽減策として、今後の議論の焦点となる可能性は高いと言えます。
◆シナリオ③:「EV一辺倒」に待ったがかかる?
世界的な脱炭素の流れの中で、自動車の未来はEVにある、という見方が主流になりつつあります。
しかし、高市氏は過去のインタビューで、「EVだけが唯一の選択肢ではない」という考えを明確に示しています。
これは、日本の自動車業界が得意としてきたハイブリッド車(HV)や、充電もできるプラグインハイブリッド車(PHEV)の価値を、もう一度見直すというメッセージとも受け取れます。
日本のエネルギー事情やインフラ整備の状況を鑑み、多様な選択肢を残すという現実的な路線が、今後の政策議論の中でより重視されるようになるかもしれません。
◆シナリオ④(リスク分析):専門家が懸念する「貿易」への影響
最後に、リスクシナリオについても触れておきます。
高市氏は、安全保障などの分野で、特定の国に対して毅然とした姿勢で臨むことで知られています。
そのため、一部の専門家の間では、それが主要な貿易相手国との関係を緊張させ、日本の最大の輸出産業である自動車業界が、思わぬ対抗措置などのリスクに直面する可能性を指摘する声もあります。
もちろん、これはあくまで将来的なリスクの一つであり、現時点で確定しているわけではありません。
しかし、世界を相手にビジネスをする自動車業界にとって、国際関係のバランスは常に考慮すべき重要な要素です。
不確かな未来だからこそ、今を知ることが重要になる

本稿では、日本の自動車業界の未来について、確定路線と予測されるシナリオの両面から考察しました。
確実なのは、半導体支援に代表される「経済安全保障」の路線が、今後さらに強化されていくことでしょう。
これは、日本のモノづくりを守るための重要な基盤となります。
一方で、ガソリン減税(トリガー条項)やEV一辺倒ではないエネルギー政策への転換は、高市氏の過去の発言から「可能性」として浮上しているが、今後の政権運営の中で具体化されるかはまだ不透明です。
確かなことと、これから起こるかもしれないこと。
その両方を把握することで、私たちは今後の動向をより深く理解することができます。
新しいリーダーのもとで、日本のクルマ社会がどんな未来へと進むのか、引き続き注目されます。
お問い合わせ・ご相談
カーコーティング、プロテクションフィルム(PPF)に関するご質問や、お見積もりのご依頼など、お気軽にお問い合わせください。
本フォームは、お客様からのお問い合わせ専用です。営業・勧誘目的でのご利用は固くお断りいたします。ご入力いただきましても、ご返信はいたしかねますのでご了承ください。